
「小学校入学まであと半年!」
年長の秋〜冬になると、ランドセルも届き始め、「いよいよだな」と実感する時期ですよね。
私自身、息子が小学1年生になる前は期待と不安が入り混じり、毎日のように「入学準備って何をしたらいいの?」と検索していました。
そして今、息子は小学3年生。振り返ってみると「入学前にやっておいて本当に良かったこと」と「もっとやっておけばよかった!」と思うことがたくさんあります。
今回は、これから小学校入学を迎えるご家庭に向けて、先輩ママのリアル体験から学んだ「入学までの半年でやっておいた方がいいことリスト」をご紹介します。
目次
1. 基本的な生活習慣を整える
早寝早起きのリズムをつける
小学校生活で最も大切なのは生活リズム。
入学後は朝8時前後に登校するため、年長のうちから「朝7時までに起きる」習慣をつけることがおすすめです。
→ 早めの時間に登園しているお子さんでしたら大丈夫ですが、我が家は1時間出発時間に差があったので、冬休み明けから準備しました。
朝ごはんを自分で食べ切る
保育園や幼稚園では多少食べ残してもフォローしてもらえますが、小学校では自分で食べて出発が基本。
偏食がある子は特に、入学前に「朝に食べられる定番メニュー」を決めておくと安心です。
配膳、食器を運ぶ練習
1年生の始めの頃は先生が配膳してくれたようですが、徐々に給食当番が始まります。
ご飯やサラダなどの配膳から始めて、食べ終わったお皿を自分で下げる練習をしておくと給食当番が始まったときにスムーズです。
→エプロン、三角巾の着脱を自分で出来ない子多数とのことなので、巾着から出して着る、脱いで巾着にしまうという練習もしておくと良いかと思います。
2. 学習の土台づくり
名前の読み書き
入学後、すぐに自分の名前を書く場面が増えます。
・連絡帳
・持ち物の記名
・テストやプリント
字が下手でも大丈夫。まずは「自分の名前をひらがなで書ける」ことを目標にしましょう。
→息子の学校での始めの授業は自分のフルネームと似顔絵を書いた名刺を3枚作り周りのお友だちと交換するというものでした。ひらがな自体は授業で習うのですが、名前は書けて当たり前というところからスタートのようで私は少し焦りました。
② 数の概念(10まででOK)
「10まで数える」「指で数を合わせられる」「簡単なたし算・ひき算の感覚」程度で十分です。
色々なキャラクターのドリルが出ているので、好きなキャラクタードリルを買ってあげるとやる気アップを計れます。
本や絵本に親しむ
小学校では国語の授業が始まります。入学前は音読の練習より「本を楽しむ時間」を大切にすると良いです。
→1年生頃は自分たちで読むというより先生が読んでくれた文章をしっかり聞いて目で追うということが大切なようでした。息子は文章を目で追うことが苦手で、先生に相談したときに風船バレーをおうちでたくさんやると、楽しくものを目で追い続ける力が身についたりすると教えていただいたので、是非試してみてほしいです。
3. 自分のことを自分でやる練習
着替えを自分で
体育の授業では5分ほどで着替える必要があります。園では先生が手伝ってくれますが、小学校では基本的に自分で。
冬場のタイツやボタン付きの服、夏場の水着は特に練習しておくと安心です。
上履き・靴の脱ぎ履き
意外と盲点なのが「靴をサッと履けるかどうか」。
体育の授業では靴を何度も脱ぎ履きするので、マジックテープ式の靴がおすすめです。
ランドセルの扱い方
ランドセルを背負って歩くだけでも大変!そして意外と、ランドセルの開閉につまずくことも、、、入学前から背負って通学路を歩く練習をしましたが、これがとても役立ちました。
トイレの使い方
まだ小学校には和式トイレがあるところもあり、遠足で行く公園には和式トイレしかないことも、、、
小学校に入って和式トイレを初めて見て戸惑うということがないように、出来れば事前に練習むずかいようでも一度は見せておいて、こういうトイレもあるということを教えておくと良いです。
4. 入学準備品の確認と使い方
学用品の名前つけ
鉛筆、消しゴム、定規、ノート…入学時は数十点に名前を書かなくてはなりません。
※入学当初は鉛筆や消しゴムを無くして帰ってくること多数なので多めに用意しておいてください
→ 名前シールやスタンプを使うと時短になります。
文房具の使い方練習
・鉛筆を正しく持つ
・消しゴムを使う
・定規で線を引く
授業ではあまり時間をとって教えてもらえないし、これらは入学後すぐに必要です。入学前に少し遊び感覚で練習すると安心です。
いざという時のためのグッズの確認
小学校ではキッズスマホが禁止のところも多く、うちの息子の学校でも持ち込みを禁止されています。
なのでGPSを持たせるのか?そのGPSも音声やりとりができるものなど種類も多数ですし、使い方はしっかりと確認が必要です。
入学式で防犯ブザーが配られる学校も多くあるので、防犯ブザーの使い方、万が一間違えて鳴ってしまったときの止め方も練習しておくと親子の安心に繋がります。
5. 心の準備
① 先生や友達に「助けて」と言える練習
幼稚園、保育園のように先生の目が行き届かないのも事実なので、場面緘黙症や人見知りのあるお子さんは特に、声を出せないときの代替手段を用意すると安心。
→ 我が家では「カードに絵を描いて伝える」方法を練習しました。
② 小学校見学
可能であれば学校での説明会や検診のときに少し教室を覗いてみたり、トイレへ寄ってみたり、校舎や教室に触れておくと不安が軽減されます。
③ 入学後の見通しを伝える
小学校生活についての絵本を読み聞かせたり、「小学校は1時間ごとにチャイムが鳴るよ」など、簡単に流れを伝えるだけでも子どもは安心します。
6. 保護者がやっておくべきこと
① 学童や放課後の過ごし方を検討
共働き家庭では特に重要。見学・申し込みを早めに済ませると安心です。
② PTAや学校のルールを確認
入学説明会で配られる資料はしっかりチェック。集金袋や提出物の締切管理なども意識しておきましょう。
③ 子どものメンタルを支える
入学準備で焦ると子どもにも不安が伝わります。
息子の学校説明会のときに先生が「これが出来ないと先生に怒られるよ」と言った声かけは避けてくださいとお話しがありました。
「できなくても大丈夫だよ」と安心させる言葉がけが、入学前の最大のサポートです。
まとめ|“完璧”じゃなくていい。少しずつ準備すればOK!
入学準備と聞くと、つい「勉強をしっかりさせなきゃ」と思いがちですが、実際に小学校生活で大切なのは、生活習慣・自分のことを自分でやる力・安心して過ごせる心の準備です。
小学3年生になった今だからこそ言えるのは、「完璧にできなくても大丈夫」ということ。
入学してから先生や友達に学ぶこともたくさんあります。
焦らず、半年の時間を“楽しく準備する期間”ととらえて、親子で一歩ずつ進めていきましょう。
関連記事
↑現在3年生の息子の入学説明会のときにもらった冊子が元になっている記事なのでお時間ある方は是非読んでおいてください。
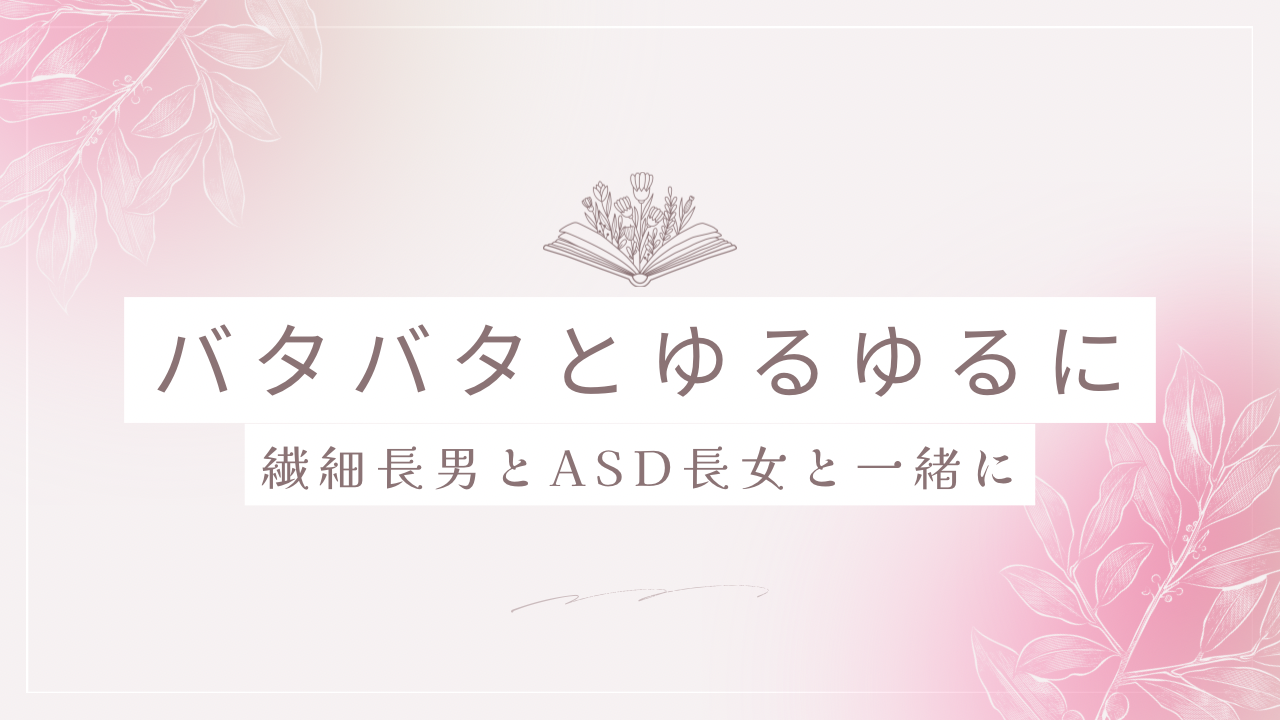
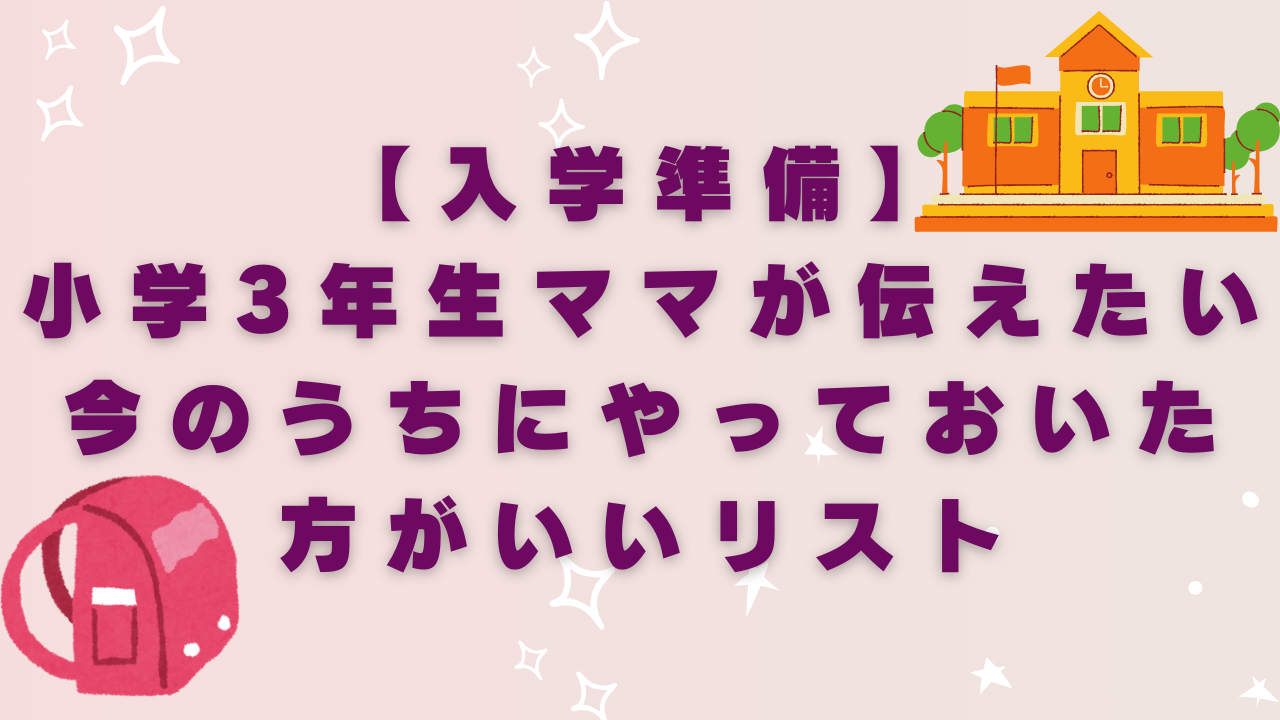






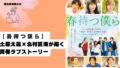
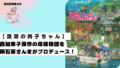
コメント