
吉沢亮さん主演で両親役には実際に聴覚障害を抱える俳優さんを起用している『ぼくが生きてる、ふたつの世界』2児の母で軽度嘔吐恐怖症のわたしがご紹介します。
あらすじ

宮城県の小さな港町、五十嵐家に男の子が生まれた。祖父母、両親は、“大”と名付けて誕生を喜ぶ。ほかの家庭と少しだけ違っていたのは、両親の耳がきこえないこと。幼い大にとっては、大好きな母の“通訳”をすることも“ふつう”の楽しい日常だった。しかし次第に、周りから特別視されることに戸惑い、苛立ち、母の明るささえ疎ましくなる。心を持て余したまま20歳になり、逃げるように東京へ旅立つ大だったが・・・。(公式サイトよりhttps://gaga.ne.jp/FutatsunoSekai/about.html)
嘔吐恐怖症の方は観られる??
直接的嘔吐シーンはありませんが、でんでんさん演じる祖父が泥酔して帰ってきたり、主人公の大と要介護となった大の祖父が話しているときに、咳き込み苦しそうなシーンがあり、でんでんさんの演技力も相まってわたしは少しドキドキしてしまいました。
子どもと一緒に楽しめる?
映倫では特に年齢制限は設けられておりませんでしたが、Netflixでは13歳以上の鑑賞を推奨しています。
過激なシーン、残虐なシーンはありませんが、ヤクザ上がりの祖父の入れ墨や閉鎖的な港町特有の雑な言葉遣いや耳が聞こえないことによる同情と差別の間のようななんとも言えないシーンが多くあるので13歳以上だと理解した上で観ることができるかなと思います。
こんな方におすすめ
✳︎聴こえない世界のことを少し知りたい方
✳︎親子の記録を観たい
✳︎実話を元にした映画が好きな方
✳︎手話を題材にした作品に興味がある方
✳︎コーダと呼ばれる(聴こえない、聴こえづらい親をもつ聴こえる子ども)方のことを知りたい方
ネタバレあり感想
公開当時の劇場数が少なかったことから、映画自体を知らなかったのですが、Netflixで配信されたことをきっかけに鑑賞いたしました。
聾学校で出会った2人が結婚し、産まれたのが主人公の大(吉沢亮)で大の祖父母は両親共に耳が聞こえないことから反対するも2人はとても幸せそうで観ていると自然と顔がほころぶような幸せな場面でしたが、耳が聞こえない中の育児は想像以上に大変で危険が多く、母親の両親の手伝いがあっても育児中の身からするとヒヤヒヤするシーンが多かったです。特に印象的だったのは、赤ちゃん期に夜泣きに気づくために大の足と母親の腕を紐で結び動いたときに気がつけるように工夫するもすぐには気づかず泣き続けている赤ちゃんの姿には胸が苦しくなりました。
幼少期は不自由ながらも愛情いっぱいで育てられたこともあり、買い物先や道中で聴こえない母のことを手伝っていた大も学校へ行きだすと次第に手話で話すことや聞こえないながらも発声して話す母親に対して恥ずかしさを抱くようになり、参観日を教えなかったり、外で手話を使うことを避けたりします。そこには、同級生に「お前のお母さん話し方変じゃない」と言われたり、手話を教えていた同級生におもちゃのように扱われたりしたどちらも悪気はないものの大にとって自分の家は他と違うと意識づけられてしまった背景がありました。閉鎖的な町で可哀想という目同情の目や差別の目に晒された大は近所の家の花が踏み荒らされたときに犯人扱いを受けます。ただ、何を言っても聞いてくれない近所の人に母親は言い返して大を庇ったことが不幸中の幸いのように感じました。
中学生からは吉沢亮さんが大を演じているのですが、すごい!!まぁ大人びて見えるものの苦労した幼少期からくるものに感じなくもないし、大人が混ざってる感が薄くて驚きました。思春期と高校受験で苛立つことが多くなり、受験経験がない両親や教育相談に来ても先生の言っている内容を理解できない母親に強い苛立ちをみせるもなんとか塾で勉強し、先生からも安全圏と言われた高校を受験するも落ちてしまい、そのとき初めて面と向かって母親に怒りをぶつけます。「普通の家だったら」「何も相談にのってくれなかった」ずっと大の中にあったモヤモヤが溢れ出るシーンは母親として観ていると苦しく、そのときの母親が反論するでも泣くでもなくただ悲しそうな、申し訳なさそうな表情をしているのが余計苦しかったです。
それから色々な過程を経て上京し、手話を通じて知り合ったサークルの人から、聴こえない親から育った聴こえる子どものことをコーダといって2万数千人程いるということを教えられます。自分と同じような人が思ったより多くいること、その状態に名前があることは大にとって発見であり、支えのようなものだったのではないかなと思いました。
その手話サークルの人たちと関わる中で、飲食店で代わりに注文を言ってあげたりしていた大に「わたしたちからできることを取らないでほしいの」と伝えていたのが印象的で、自分のできること全てをやってあげて手を差し伸べることだけが優しさではないということを感じると同時に聴こえる人もそれぞれ違うように聾の方にもそれぞれ違う手の差し伸べ方があるんだろうなと思いました。
上京してから8年もの間実家に帰ることがなかった大が帰るキッカケになったのは父親が事故に遭った知らせを受けて。一命は取り留めたものの入院している父親に介助が必要となった祖母、そして聴こえない母親、自分から実家に戻ることを提案するも母親からはいつもの笑顔で一蹴される。東京に帰る駅のホームで大が思い出したのは上京前に母親と買い物をした日のこと。スーツを買ったりパスタを食べたりしながら帰りの電車でも話しが途切れることなく過ごした日、そんな日の最後に母親から言われた「恥ずかしがらず手話で話してくれてありがとう」という言葉。
この映画は聴こえない両親と聴こえる子どものコーダを取り扱った映画ですがそれ以上に、普通の親子の話だったんだ、と深く感じました。
慣れない育児に試行錯誤し、思春期や反抗期で親子の距離が少し離れて心ない言葉をかけられることもあり、それでもやりたいことのために背中を押し、反抗期が明けた子どもと普通に会話できたことに嬉しくなり、離れた子どもを心配しながら荷物を送る。子どもに心配かけないようにまた送り出す。そんな親としても子どもとしてもどこか身に覚えがあるような温かい家族の話でした。
もちろん実話を元にしているからこそ、コーダとしての苦悩や聴こえない方達の意見も垣間見ることができて考えるキッカケにもなります。また実際にろうの方の俳優さんが多く出演されているので発声や手話をリアルに感じられるかと思います。
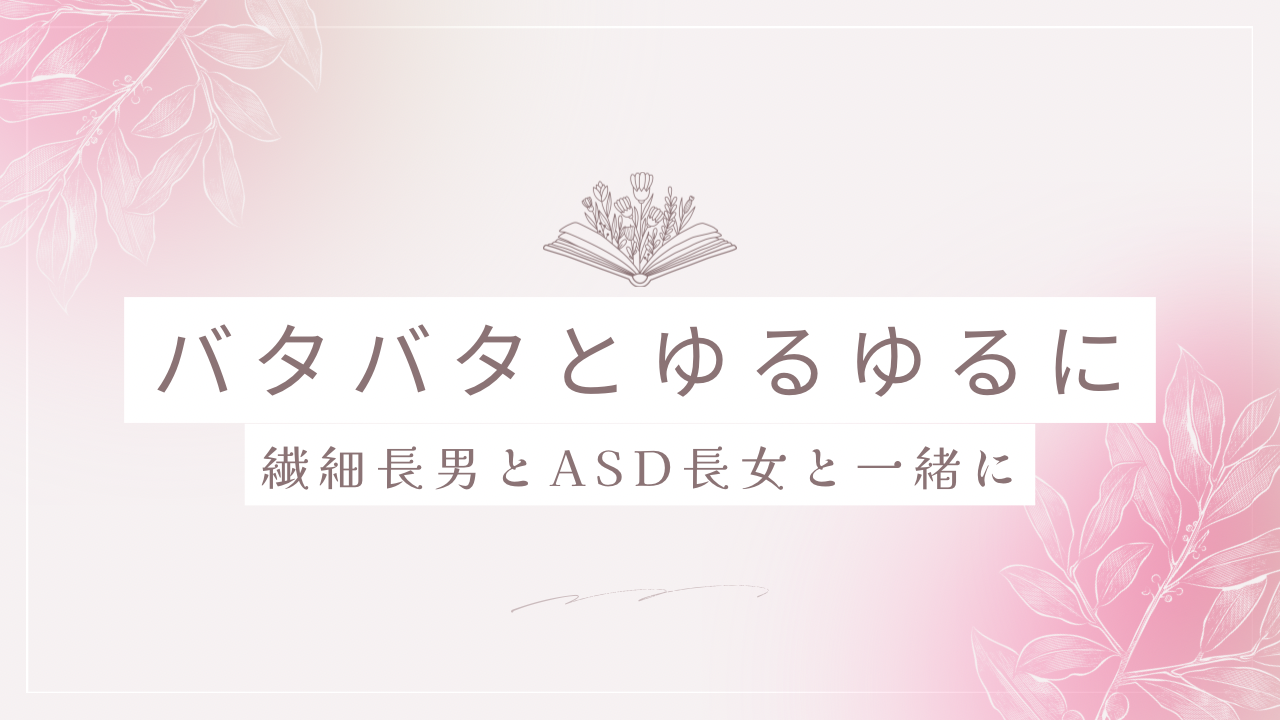
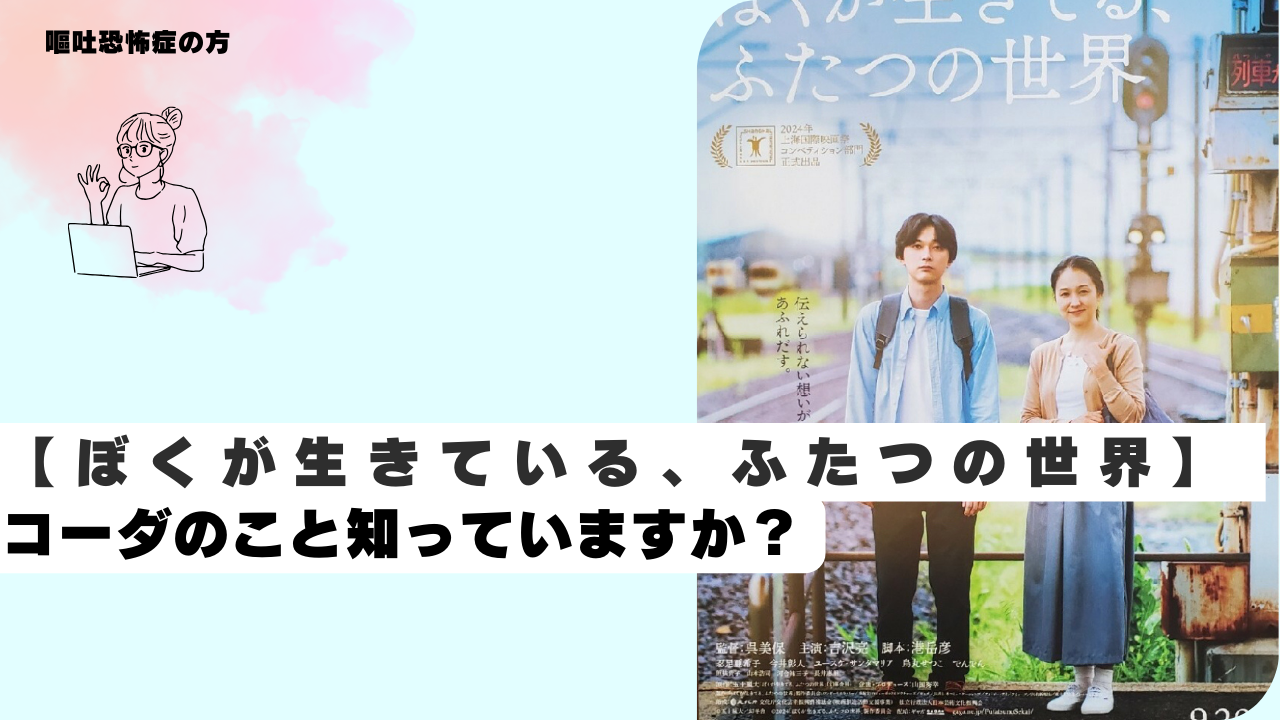
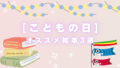

コメント