
子どもが「場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)」と診断されたとき、保護者として最初に悩むのが 園の先生への伝え方 ではないでしょうか。
「どう説明すれば理解してもらえる?」「迷惑をかけてしまわないかな?」と不安になる親御さんは少なくありません。
私自身も、6歳の娘が場面緘黙症とわかったとき、まずは担任の先生にどう話すべきか迷いました。
今回はその経験をもとに、園の先生へ伝えるときの工夫やポイントをまとめます。
目次
なぜ先生への伝え方が大切なのか?
- 園生活の大部分を先生がサポートするため、情報共有は必須
- 先生が「緘黙=ただの人見知り」と誤解してしまうこともある
- 正しい理解があると、無理に話させようとせず、子どもが安心できる環境を作れる
先生への伝え方次第で、子どもの園生活の安心度や成長スピードが大きく変わると感じています。
先生に伝えるときの基本ポイント
① 医師の診断や専門機関の資料を用意する
「場面緘黙症」という言葉に馴染みがない先生も多いため、診断書やパンフレットを見せるとスムーズ。
具体的な症状や対応法が書かれている資料は先生にとっても参考になります。
② 「家庭では話せる」という事実を伝える
「家では元気に話している」ことを強調すると、先生も「言葉が出せないのは環境のせい」と理解しやすいです。
③ 「無理に話させないでほしい」とお願いする
緘黙の子は「話さなきゃ」と追い込まれるほど声が出なくなります。
先生には「声を出すことより、安心して過ごせることが第一」と伝えましょう。
④ 具体的な配慮を伝える
- 発表のとき、固まっているような様子があれば先生が代読してほしい
- 点呼は手を挙げるだけでOKにしてほしい
- 給食の「いただきます」なども無理強いせず、表情や動作で参加できれば良しとする
もちろん何かのキッカケで声が出ることもあるかもしれないので、完全に機会をなくすのではなく、トラウマやプレッシャーにならない程度に機会を与えてほしいけど、固まっている状態で視線が集中し続けることはなるべく避けてもらうようお願いしました。
こうした「代替手段」をあらかじめ伝えておくと、先生も対応しやすいです。
実際に私が先生に伝えた方法(体験談)
娘が年小のとき、私は担任の先生に次のように伝えました。
- まず「人見知りではなく、場面緘黙症という特性です」と説明
- 家ではおしゃべり好きであることを伝え、病気ではなく「心の反応」であると強調
- 「話さなくても、参加できていれば大丈夫」とお願い
- 発表や行事のときは必要に応じて代読をお願いする
このように伝えたことで、先生も安心した様子で「なるほど、そういう子なのですね」と受け止めてくださいました。
結果として、娘も園で「声を出さない自分」を否定されずに済み、安心して園生活を続けられました。
伝えるタイミング
- 年度初めの面談:新しい担任に最初から理解してもらえる
- 行事の前:発表や発言が求められる前に伝えておくと安心
- 普段の連絡帳:日常の小さな困りごとを先生と共有できる
「特別に時間をとって伝える」よりも、日常のやりとりの中で自然に話す方が負担が少ないです。
先生への伝え方の工夫
- 「お願いベース」で伝える
「こうしてください」ではなく「こうしていただけると助かります」という言葉がけだと受け入れやすい。 - 否定しない
「もっと声を出させてください」と言われても「でも、それは無理です」ではなく、「本人のペースを優先したい」と前向きに返す。 - 一緒に考える姿勢
「園と家庭で協力してサポートしたい」と伝えると、先生も協力的になります。
困ったときのサポート先
- 発達支援センター:先生向けのアドバイス資料を用意してくれることもあります
- 臨床心理士やST(言語聴覚士):先生と連携しやすいように助言してくれる
まとめ
保育園・幼稚園の先生への伝え方で大切なのは、
「無理に話させないこと」「本人の安心を優先すること」 を伝えること。
先生に理解してもらえれば、子どもにとって園が安心できる居場所になり、少しずつ声が出るきっかけにつながります。
私自身、勇気を出して先生に伝えたことで、娘の園生活が大きく変わりました。
同じように悩むママ・パパの参考になれば幸いです。
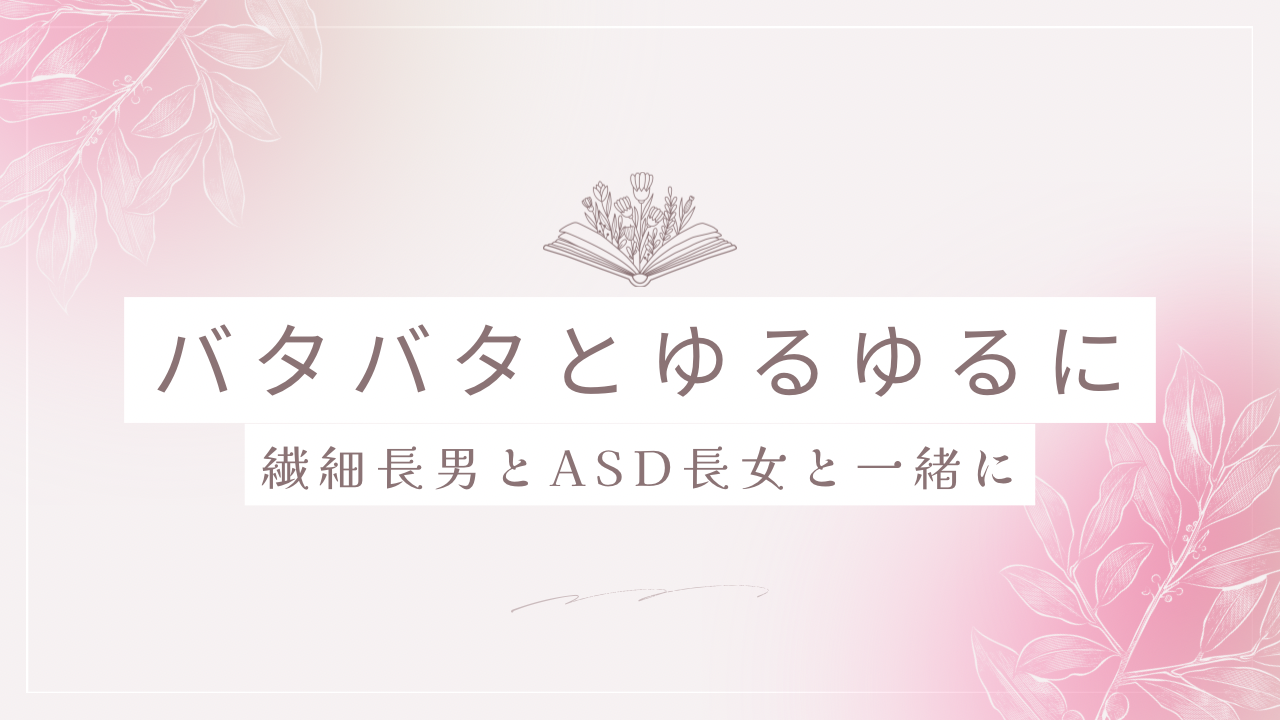
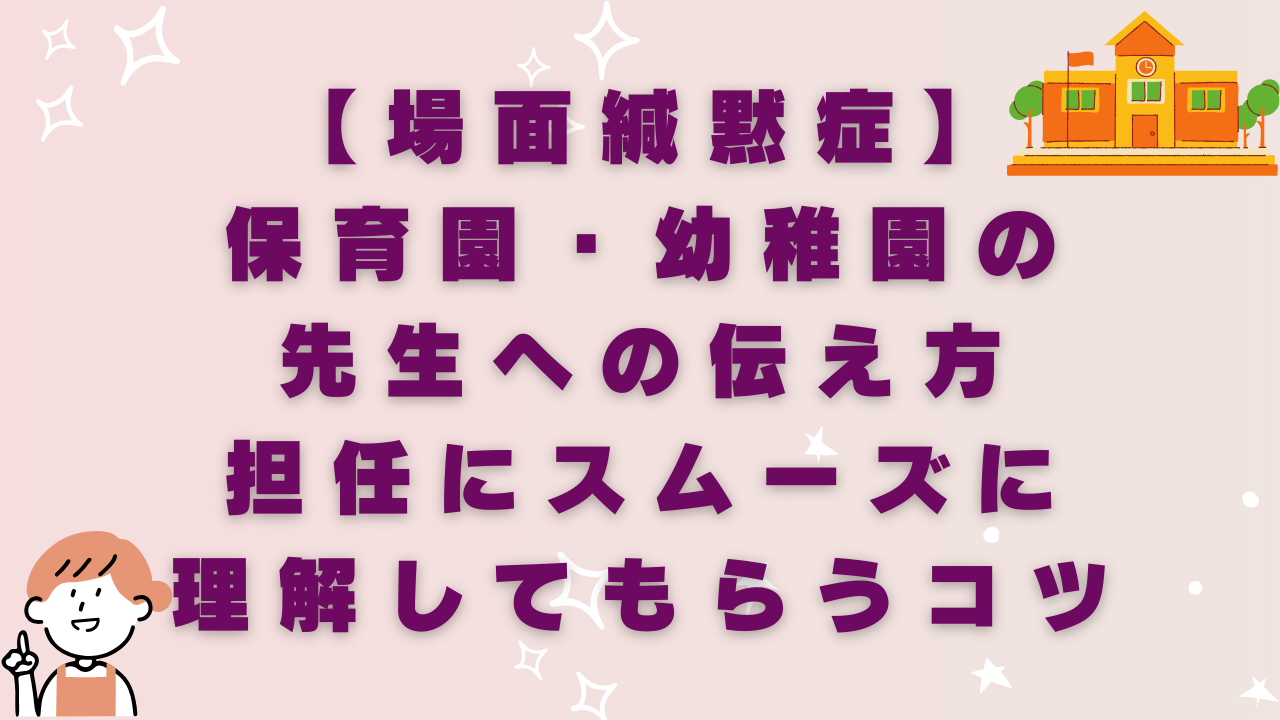
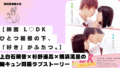
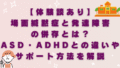
コメント