
こんにちは。6歳の娘を育てている母、ゆるです。
今回は、園で話すことができなかった娘が、少しずつ変わっていった過程について、先生との連携を通じて見えてきた「気づき」と「成長」を中心に書いてみたいと思います。
娘は場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)と診断されています。
家庭ではよく話し、よく笑う娘。でも、園では2歳の頃から年長の現在に至るまで、ずっと「声を出せない」状態が続いていました。
そんな娘に、どのように園が関わってくれたのか。そして、どんな小さな変化があったのか。
同じように「園で声が出ない子」を育てている親御さんに、少しでもヒントになれば幸いです。
目次
「家庭と園で違いすぎる娘」に感じた戸惑い
娘が2歳で入園したころ、担任の先生から言われたひとことが印象に残っています。
「娘ちゃん、まだ声を聞いたことがないんです」
私は正直驚きました。
家では、絵本の読み聞かせを真似してみたり、CMで聞いたた歌を口ずさんだりと、よくしゃべる子だったからです。
当初は元々人見知りをする子ではあったので「場所見知り」「恥ずかしがり屋」だと思い、自然に慣れるのを待っていました。
しかし、半年が過ぎても一言も声が出ない日々が続き、ようやく「何か違う」と感じるようになりました。
園の先生との情報共有が、はじめの一歩
私たち親が娘の状態について真剣に向き合うようになったのは、3歳になったころ。
家では普通に話すのに、園では一切話さない。
本人は困っている様子はなく、でも明らかに「話せない状況」が続いている——。
先生に正直に相談しました。
「実は、家では本当によくしゃべるんです」
「でも、園ではまだすごく緊張してしまうみたいなんです」
それを聞いて先生がすぐに理解してくださったわけではありませんでしたが、
少しずつ「話さない=反抗的」「困った子」ではない、という認識を持ってもらえたように思います。
そして、そこから「園と家庭が協力して、娘を支えていく」という意識が生まれました。
先生と連携して実践した3つの工夫
園と家庭で連携しながら、以下のようなことを取り入れました。
① 話さなくても伝わる方法を用意する
園では、娘が安心できるように「YES/NOカード」「助けて!カード」を使って気持ちを伝える工夫をしてくれました。
話せない=意思疎通ができないわけではありません。
ただ、先生からの問いかけに返答できないもどかしさや、制作物がわからないときに助けを求めたり、トイレへ行きたいと言うことを伝えられないことへの不自由さは娘も感じていました。
「どうしたいのか」を、話さずにでも伝えられる手段があるだけで、娘の表情が少しずつ和らいできました。
② 同じ先生が継続して関わる
娘の園では毎年クラス替えがありそれに伴って担任の先生が代わってしまうのですが、全体を見てくれている補助の先生が数人いてクラスメイトや担任の先生が代わっても関わり続けてくれる先生がいたことも大きかったです。
新しい人が苦手な娘にとって、「安心できる存在が変わらないこと」はとても大きな支えでした。
同じ先生が、決まった言葉かけ、決まった距離感で関わってくださることが、「信頼」の土台となっていったのだと思います。
③ プレッシャーをかけない環境づくり
先生も「声を出そうね」とは一切言いませんでした。
「絵が描けたら見せてね」「カードで答えてもいいんだよ」など、声を出すこと以外の成功体験を積み重ねてくれたことが、娘にとって大きな安心材料でした。
少しずつ見えてきた変化
年長の春ごろ、娘が先生に小さな声で「うん」と頷くようになりました。
声は出ていない。でも、口を動かすだけでも娘にとっては大きな一歩でした。
ある日、担任の先生が言いました。
「娘ちゃんが今日、声は出てなかったけど“うん”って口を動かしてくれました。あれはすごくうれしかったです」
その話を聞いて、私は涙が出ました。
娘は今も園でお友だちと話すことはできません。
でも、「できないこと」に注目するのではなく、「できたこと」を先生と一緒に喜び合える。
そんな環境が、娘を少しずつ変えてくれたのだと感じています。
話せなくても、伝えたい気持ちはある
場面緘黙症の子どもたちは、「話したくない」のではありません。
「話したくても話せない」「声が出ない自分に戸惑っている」のです。
そのことを理解してくれる大人がひとりでもいることで、子どもは安心し、「伝えたい」「関わりたい」という気持ちを少しずつ表に出せるようになります。
おわりに|園との連携が子どもと自分を支える
娘が園で一言も話せなかった期間は、もう3年近くになります。
でも、その間に「声」以外の方法で気持ちを伝える力、他者と関わる力は確実に育ってきました。
そしてそれは、家庭だけでは難しかったと思います。
園の先生方と連携し、同じ方向を向いて支えてこれたことが、娘の心の土台を育ててくれたのです。
そして、”話せない娘”にどうしてあげることがいいか悩む私と一緒に対策を考えたり、成長を喜んでくれる家族とはまた違う理解者がいるということは親である私自身も救われました。
話せなくても大丈夫。
子どもたちは、自分のペースで、ちゃんと前に進んでいます。
もし今、同じように悩んでいる親御さんがいたら、どうか焦らず、信じて待ってあげてください。
それがきっと、子どもにとって一番の「安心」になります。
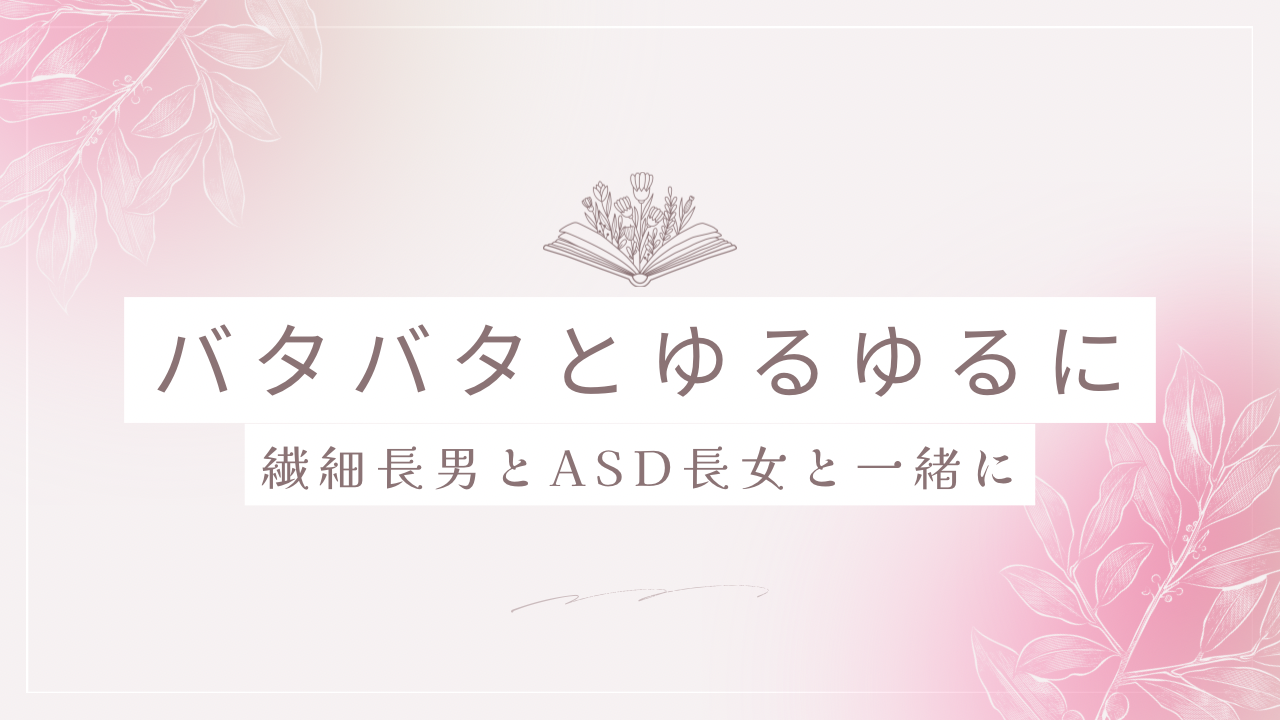
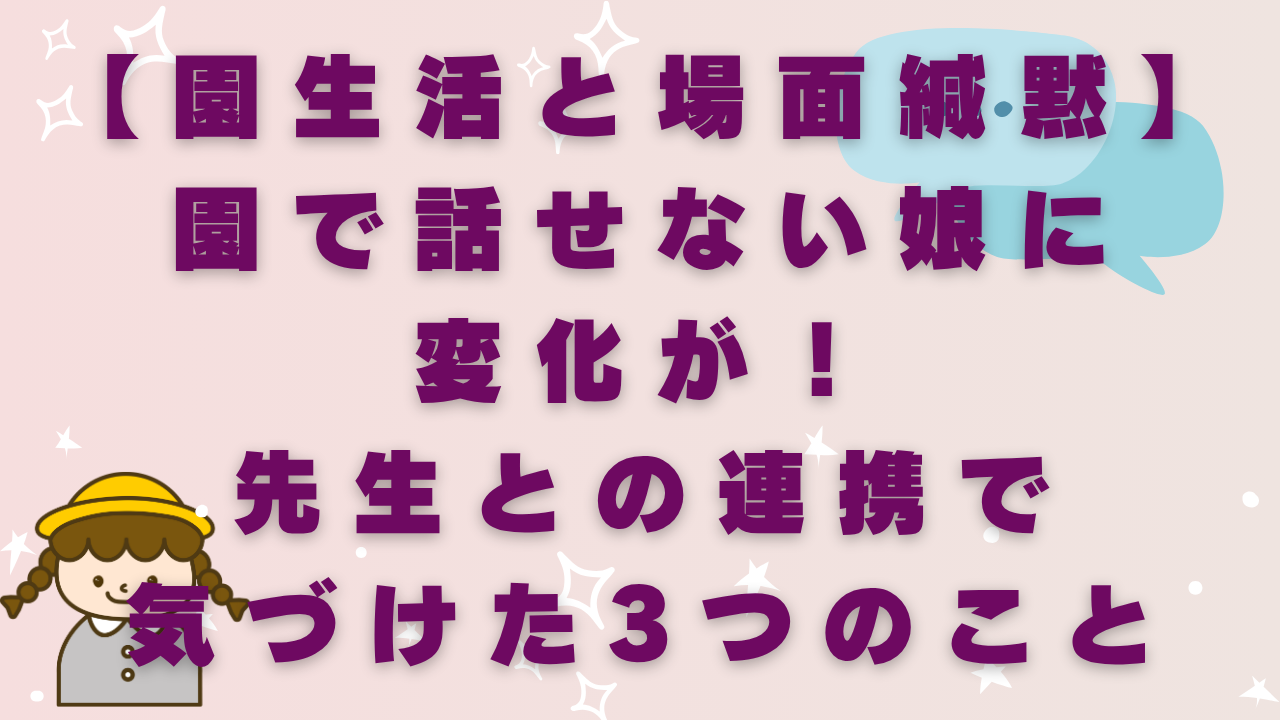
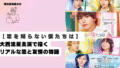
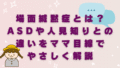
コメント