
こんにちは。6歳の娘を育てている、母のゆるです。
今回は、娘が「場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)」と診断されるまでの経緯を、私自身の経験をもとに綴りたいと思います。
同じように「保育園(幼稚園)では話さないのに、家では元気いっぱい」そんなお子さんを育てている方の参考になれば幸いです。
目次
家ではおしゃべりなのに、園では無言
娘は、2歳を過ぎたころから徐々に言葉が増え、家ではたくさんおしゃべりをする子でした。家族とはスムーズに会話ができ、好きな歌を歌ったり踊ったり。
ところが、幼稚園ではまったく様子が違いました。
4年保育の園に入園させて1ヶ月経った面談では先生からはこんな言葉をもらっていました。
「お母さん、娘ちゃん、家ではお話してますか?」
「こちらではまだ声を聞いたことがなくて……。」
「給食も一切食べれていません。」
元々人見知りや偏食ではあったので、最初は「恥ずかしがり屋だしな」「まだ園に慣れていないのかな」と思っていました。
けれど、一緒に入園したクラスの子たちが慣れていく中、娘は一向に慣れる様子もなく、笑わない、食べない、話さないといった様子は1ヶ月後も変わることがありませんでした。
そんなとき、市の3歳児検診がありそこで園での様子を相談することに、、、
「場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)」という言葉を知ったきっかけ
入園から約2ヶ月後娘は3歳になり、自治体で行っている3歳児検診へ行く機会がありました。
そこで、先生から面談時その後にも聞いていた園での様子を話すと別室の心理士さんがいる部屋へ通されました。
そこで伝えられたのが、「場面緘黙症かもしれません」という言葉でした。
始めは口頭で言われてもどんな意味なのか、そもそもどんな漢字を書くのかもわからず混乱しましたが、
同じ社会生活環境に1ヶ月以上いるのに
「話したくない」のではなく、話そうとしても体が固まって声が出ない。
家では普通に話せるけれど、学校・園・外では話せない。
……まさに、娘のことだと思いました。
小児精神科への相談と診断までの流れ
3歳児検診で娘の園での困り具合や偏食、こだわりのことを伝え、場面緘黙症や発達障害の疑いがあると伝えられるも、相談したのが専門医ではなく心理士なのでそもそも診断を下せないということや、まだ集団生活を始めたばかりということもあり、半年様子をみて変わらないようであれば再度検診センターへ行き面談、その後検診センターから子どもの心を診る専門の外来(児童精神科)へ紹介状を書いてもらうという流れでした。
※ここまでの流れで特にお伝えしたいことは、検診センターや、かかりつけ医に相談するときに強くその先(児童精神科)へ繋がりたいことを伝えてください。私は児童精神科へかかるまでに2人の心理士さんとお話ししましたが、私が発言するまで療育や通院に案内することはなく、大変さへの共感や日常生活でのアドバイスが主となっていて、様子見で時間だけが過ぎてしまうことを不安に感じました。(もちろん心理士さんの方から案内していただける場合もあるかと思います)
そして、検診センターから渡された児童精神科がある病院のリストの中から自分で病院を決め連絡していかなければいけないのですが、これがまた大変でした。児童精神科は数自体も少ないので、クリニックによっては新規の予約を受け付けていなかったり、月に1度先着電話のみ(これが中々繋がらない)だったりして、予約をとるだけでも3ヶ月かかり、更にとれる予約も1ヶ月後といった形で、娘が場面緘黙症の疑いがあると言われてから受診までは結局10ヶ月程かかりました。
そして、療育(リハビリ)を受けるために通院初日から4回に分けて発達診断を受け、見たことないくらいの膨大な予診票を書き、現時点での診断を場面緘黙症とASDの疑い(緘黙症状が強く正しい診断は出せなかった)となりました。
詳しくは初めての発達検査〜3歳娘の場合〜に記載してありますので、ご参照いただければと思います。
診断されて、ほっとした気持ちと、これからへの不安
「やっぱりそうだったんだ」という安心と、「これからどうしていけばいいの?」という不安が入り混じっていたと思います。
でも、名前がついたことで、私の育て方のせいだけではなかったことに救われました。
【5選】私が今現在通院している児童精神科を選んだ決め手
*年間通して通院しやすいか
どのくらいの頻度で通うかは始めの時点ではわかりませんが、乗り換えが少なかったり駅近だったり、近くに駐車場があるかなど。
*家から近すぎないか
まだまだ精神科という言葉に偏見がある方もいるので、まだどうなるかわからない就学前に通院を知られて線引きされることを避けるため。
✳︎言語聴覚士や作業療法士などの専門家が常勤しているか
これが中々難しく、娘は既に集団生活に入っていたため、集団での療育が主となる療育施設へは通わせずに一対一での療育が主の院内のリハビリを希望していたため、院内にリハビリ環境と専門家がいる病院を探しました。
✳︎同性が対応してくれるか
娘は異性に対する恐怖心が特に強く、親である私としても一対一で個室での療育を異性に見てもらうことに抵抗がありました。(娘は言語に遅れもあったため万が一のことがあっても本人の口から伝えられないということをわかっている異性と2人にしたくなかった)
✳︎児童精神科を主としているか
渡されたリストの中には大人の精神科の中で子どももみることができるといったクリニックも多くありましたが、なるべく児童精神科のみ、もしくはホームページに子どもについてのことが多く記載されているようなクリニックを選びました。
場面緘黙症と聞いて読んだ本【3選】
娘が場面緘黙症と聞いてから受診までの10ヶ月間、様子見と言われながらも不安でネットや本で情報収集をする毎日を過ごしていました。その中でも私がわかりやすいと感じた、タメになった本を3冊ご紹介します。
漫画なのがとにかく読みやすかったです。著者自身が幼稚園から場面緘黙症だったという体験談の本で1番体感として娘の様子や気持ちを感じることができた本でした。
こちらは専門家の方が親にできる手助け方や関わり方を紹介している本で、ついついやってしまいがちな子どもの代わりに親が先生やお友だちに伝えてしまうことの危険性などが書かれてあり大変勉強になった一冊です。
この本はたくさんの実例と共に効果のあった対処法を絵と合わせて書かれていて教育者向けでもありながら読みやすく、参考になりました。(こんなに実例があるのかと娘だけじゃないと少し安心したりもしました)
今、同じことで悩んでいる方へ
もし「うちの子、外では全然話さないけど大丈夫かな?」と感じているなら、どうか一人で抱え込まないでください。
保育園や幼稚園、かかりつけ医、療育センターなど、相談できる窓口はあります。
そして「声を出さない」のではなく、「出せない」ことがある、ということを知ってもらえるだけで、救われる親子がいます。
おわりに
このブログでは、娘と私が少しずつ前に進んできた記録を残していきます。
場面緘黙症のことを知ってほしい。
子どもたちが「安心できる環境」で育っていけるように。
そんな願いを込めて、これからも書いていきたいと思います。
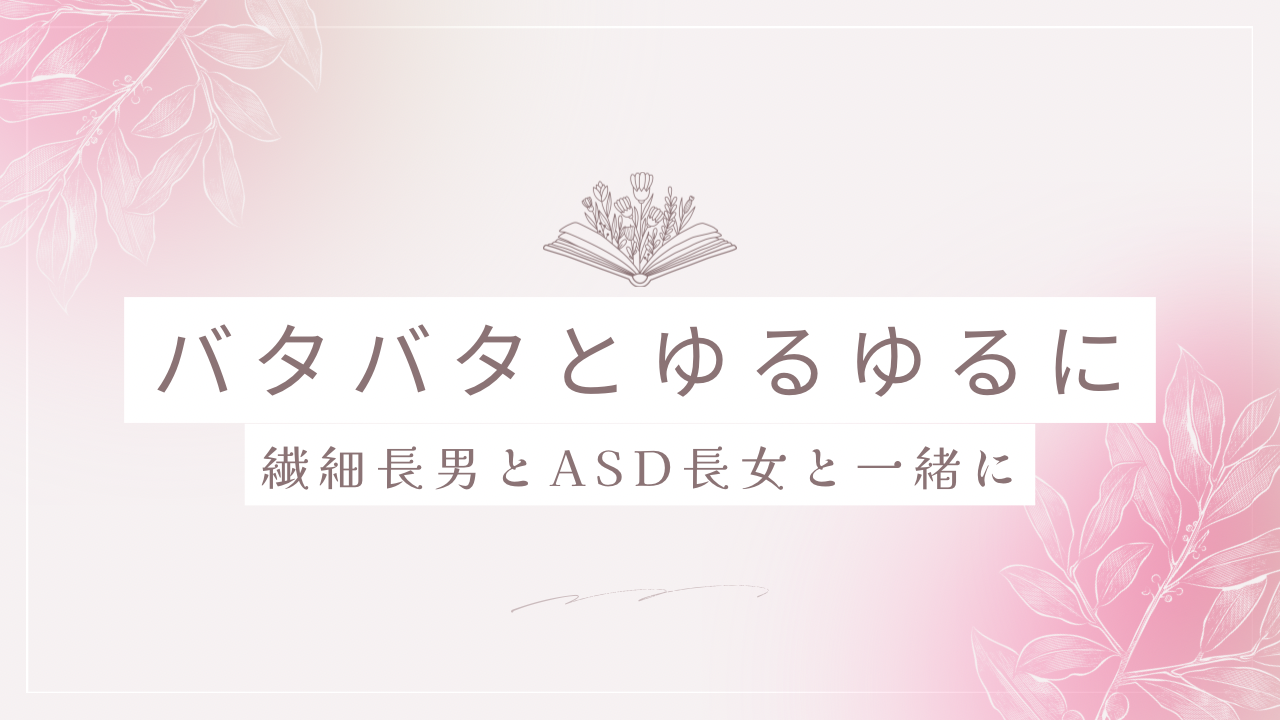
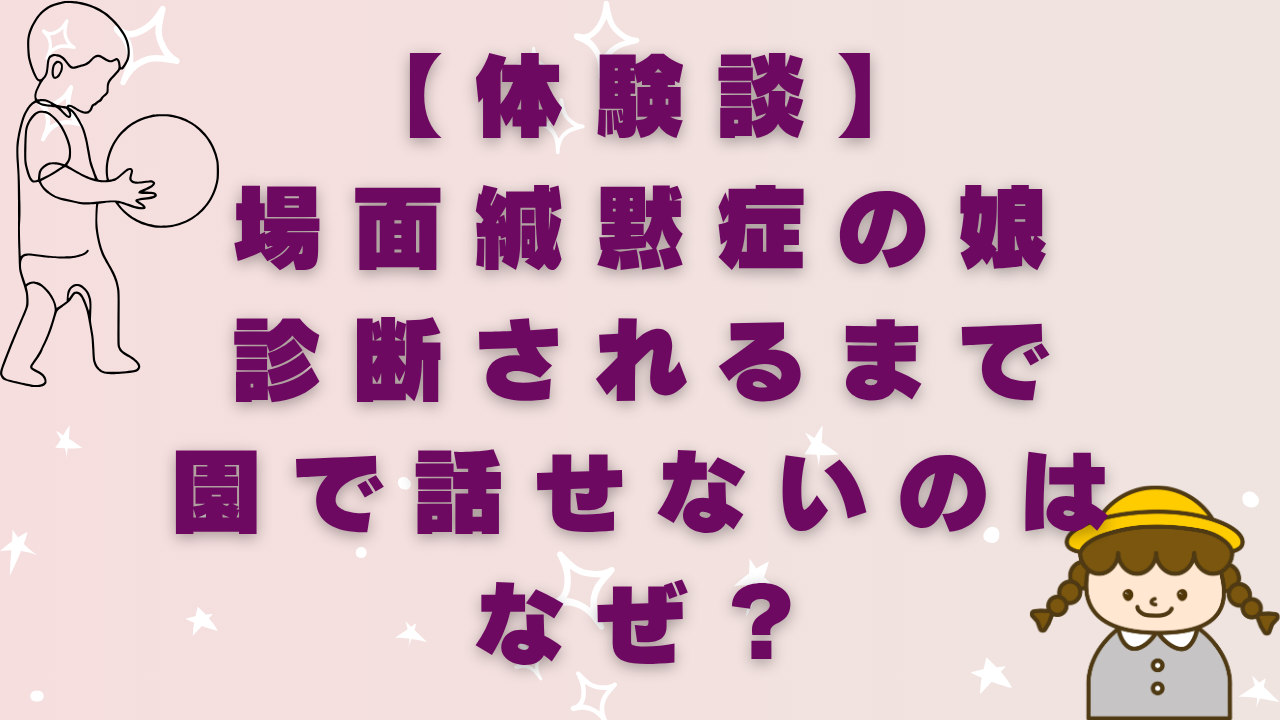



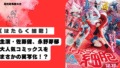
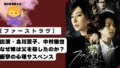
コメント