
こんにちは。6歳の娘を育てている母、ゆるです。
今回は、場面緘黙症と診断された娘との日常の中で、私たち家族が実践している「家庭でできる関わり方の工夫」についてお話しします。
うちの娘は、家では本当におしゃべりで明るい性格。でも、幼稚園ではずっと無言。入園から2年経っても、先生に一言も話せない日々が続きました。
「どうしたら、少しでも娘の安心感が育つだろう?」
「“話さなきゃ”というプレッシャーを減らせないか?」
そんな想いから、通っている児童精神科の先生や作業療法士さんなどと相談しながら私たちが試してきた5つの工夫をご紹介します。どれも専門的な知識や資格がなくても、家庭ですぐに始められる内容です。
目次
工夫① 「話す」ことを目的にしない遊びの時間をつくる
話すことを求めない遊び——それは娘にとって「安心していられる時間」でした。
例えば、
- 一緒に絵を描く
- 折り紙で何かを作る
- パズルやブロックで遊ぶ
など、言葉がなくても一緒に楽しめる時間を意識的に持ちました。
娘は、私があれこれ聞かないことで徐々に表情がやわらぎ、自然と口元がゆるみ、時にはぽつりと一言が出ることも。
娘は元々園でも制作活動は好きだったものの手先は不器用だったので折り紙などはトレーニングにもなり、幼稚園の制作物で困ることも減ったようなので、言葉ということだけではない効果を感じました。
話すことを目的にしない。でも、「あなたと一緒にいるのが楽しい」と伝える。これが、娘の自己肯定感を育てる土台になったと感じます。
工夫② 「YES/NOカード」や絵でのやり取りを使う
娘は、言葉で伝えるのが難しい場面で、表情や身振りに頼ることが多かったです。
ただ緘黙だけでなく緘動症状がでることもあったので、先生へヘルプを出すとき用に始めたのが、YES/NOカードや、簡単なイラスト(絵カード)を使ったやりとりです。
小学生くらいになっていたらお友だちへも簡単なカードを使ってコミュニケーションがとれるのかも知れませんが、娘はまだ未就学児のため先生にのみ対応をお願いしました。
本人の混乱を避けるため、『トイレ』、『痛い』、『手伝ってほしい』の3つに絞って絵とひらがなを書いたカードを持たせました。
ことばを“出す”のではなく、“選ぶ”ことで娘の気持ちが伝えやすくなりました。
工夫③ 親が「がんばって話させよう」としない姿勢をもつ
一番大きな学びだったのが、「話すことは“努力目標”じゃない」ということです。
以前の私は、
「家では話せるんだから、園でもちょっとずつ頑張ってみようよ」
と、つい励ましてしまっていました。
でもそれが、娘にとってはプレッシャーだったのです。
ある日、娘にこう言われました。
「身体がドキドキしていきなり声が出ないの。」
その言葉で、私は「今のままでもいい。話せるときが来たらでいい」という姿勢に変えることができました。
それ以来、娘も安心して気持ちを見せてくれるようになり、少しずつ“声”も聞けるようになりました。
工夫④ 毎日決まった「気持ちのふりかえりタイム」をつくる
夕方〜寝る前の5分間、娘と「今日の気持ちふりかえりタイム」をつくっています。
内容はとても簡単。
- 今日、うれしかったこと
- いやだったこと
- こまってること
これも「話す」練習ではなく、「気持ちを共有する体験」として続けています。
工夫⑤ 家族全員が“娘を焦らせない”ことを共通ルールに
私だけでなく、祖父母、兄弟も含めて、「話すことを強制しない」を家庭のルールにしました。
たとえば:
- 「なんでしゃべらないの?」はNGワード
- 返事がないときは、にっこりするだけでOK
- 話したときは、びっくりせず“さりげなく”受け止める
- 特に行事付近は本人も緊張感が強いので、結果はどうでも参加したことを褒める
話した=特別扱いになってしまうと、娘にとっては「また期待されるかも…」と逆効果になることも。
“話す・話さない”に関わらず、同じように接することが娘の安心につながりました。
おわりに|「ことば」は“芽が出るのを待つ”ようなもの
娘の声は、まるで春を待つつぼみのようだと思うことがあります。
急かしても咲かない。
でも、あたたかく見守っていると、ある日ふっと開く。
それを信じて、私たちは今日も娘と向き合っています。
この記事の内容はあくまでも娘に効果があったと感じたものを抜粋しておりますが、同じように場面緘黙の子どもと暮らすご家族のヒントになれば嬉しいです。
「ことば」が出る前に、心が安心できる環境を。
その一歩を、家庭からつくっていけたら——そう願っています。
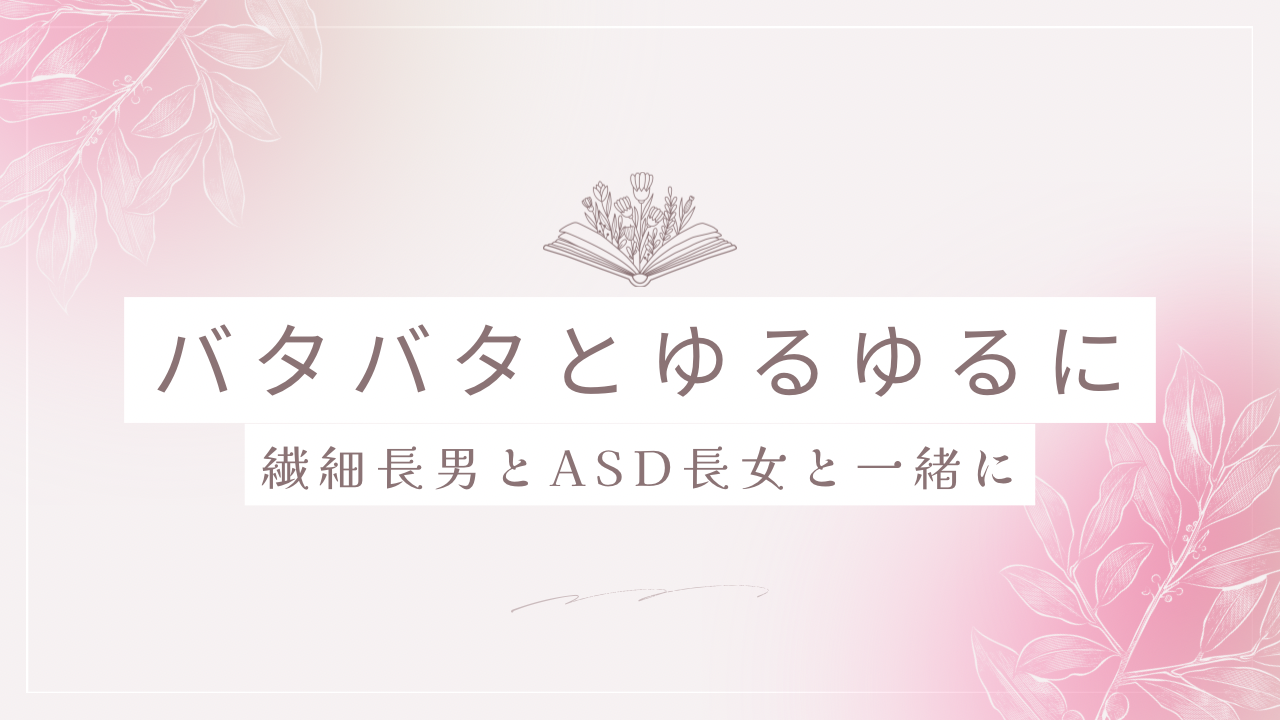
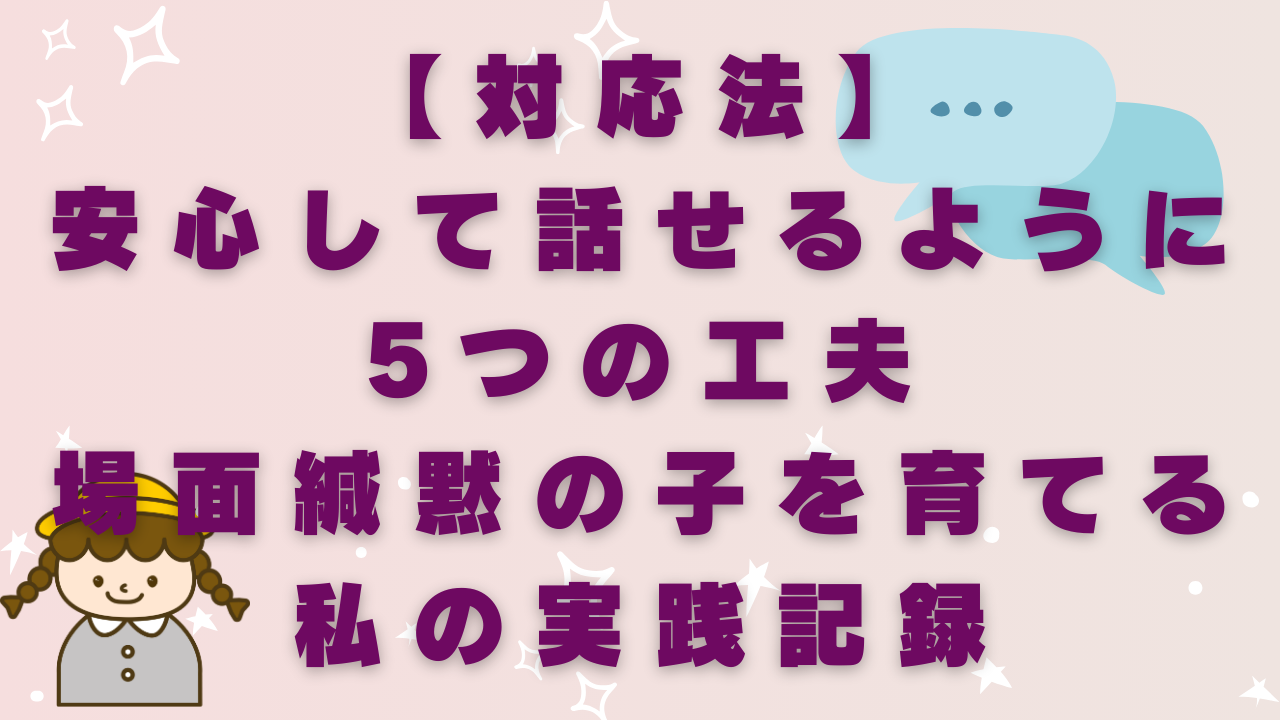
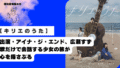
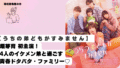
コメント