
ゆる
保育園や幼稚園の行事は、子どもにとって特別な日。
しかし、場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)の子どもにとっては、人前で話す・発表する場面が強い緊張や不安を引き起こすことがあります。
我が家の6歳の娘も、園での行事になると声が出ず、保護者として胸が締め付けられる経験をしてきました。
この記事では、行事で話せなかったときに家庭と先生でできる対応、そしてその後のサポート方法を、体験談とともにご紹介します。
行事で話せないのはなぜ?
場面緘黙症の子どもが行事で話せない背景には、次のような理由があります。
- 多くの人に見られている状況で極度の緊張
- マイクや大きな音などの感覚的な負担
- 「ちゃんとやらなきゃ」というプレッシャー
- 発表の練習が本番形式に近くなると声が出にくくなる
娘の場合も、日常の自由遊びでは笑顔で友達と遊べるのに、人前に立つ瞬間だけ急に固まるということが何度もありました。
行事当日にできる先生側の対応
- 事前に本人と流れを確認しておく
発表の順番や立ち位置、マイクの位置などを前もって知らせることで安心感が増します。 - 無理に話させない
当日は「声を出させること」が目的ではなく、「本人が安心して行事に参加すること」をゴールにします。 - 代読やジェスチャーで対応
話せない場合は先生が代読したり、手振りで参加できる形にする。
保護者ができるサポート
- 「話せなくても大丈夫」と伝える
「声を出すこと」よりも「参加できたこと」を褒める。 - 家で遊びながら練習
ぬいぐるみや家族の前でミニ発表ごっこをして、本番に似た雰囲気を体験させる。 - 事前に先生と打ち合わせ
「もし話せなかったら、こういう形で参加させてほしい」と共有しておく。
我が家の体験談
娘が年小、年中のとき、運動会と発表会で緘動の症状が出てしまい、動けなくなってしまったことがありました。
前日までは家で笑顔で練習していたのに、本番は舞台に立った瞬間に固まってしまったのです。
しかし、先生が後ろからそっと声をかけてくださった瞬間は少しだけ顔の緊張が解けたような気がしました。娘は踊ることはできなかったものの、最後まで舞台に立ち続けることができたことが大きな自信につながりました。
年長になると、少しずつ声が出せる場面が増えてきました。これは、「話せなくてもOK」という安心感が土台になったと感じています。
行事後のフォローも大切
- 成功体験を振り返る
「最後まで立っていられたね」「笑顔で手を振れたね」と行動面を褒める。 - 園での写真や動画を一緒に見る
自分が参加していたことを視覚的に確認できると自信になる。 - 次の行事への小さなステップを設定
例:「来年は少しだけ踊ってみようか?」など段階的に目標を作る。
まとめ
園の行事で話せなかったとしても、それは失敗ではありません。
無理に話させるよりも「安心して参加できた」という経験の積み重ねが、少しずつ声を出すきっかけになります。
保護者と先生が協力し、本人のペースを大切にすることで、行事は「つらい時間」から「ちょっと緊張するけど楽しい時間」に変わっていきます。
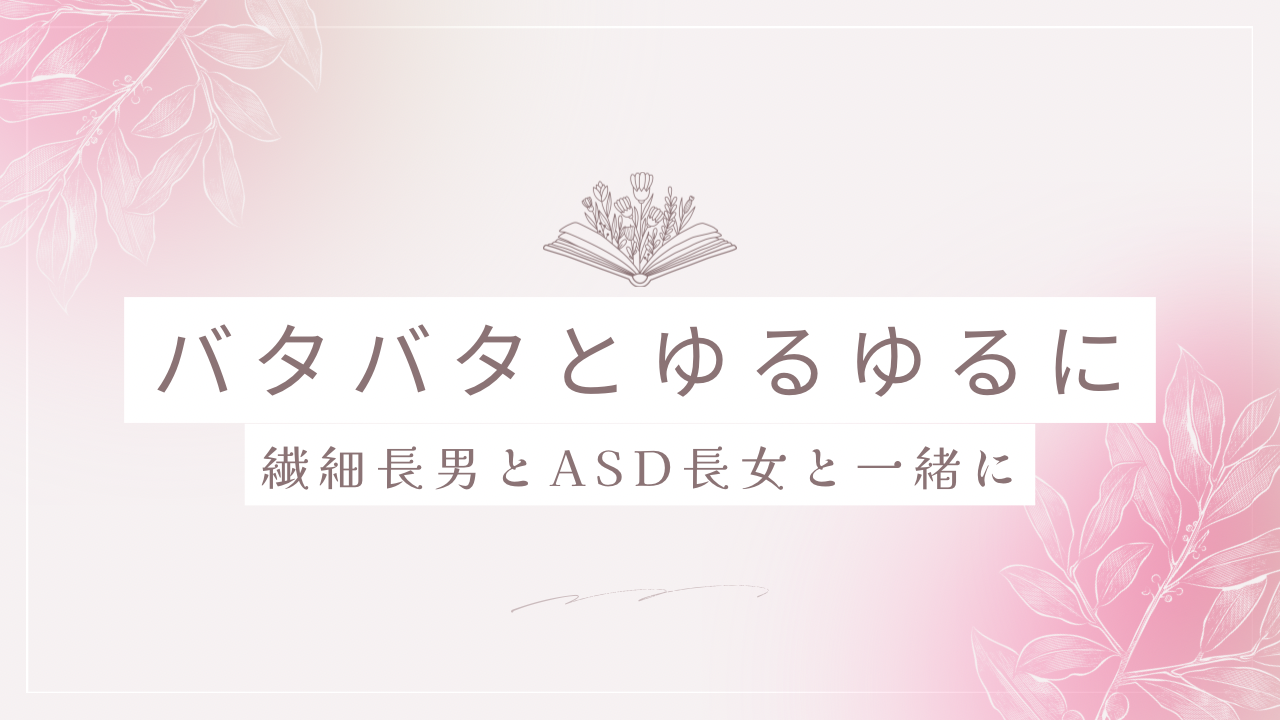
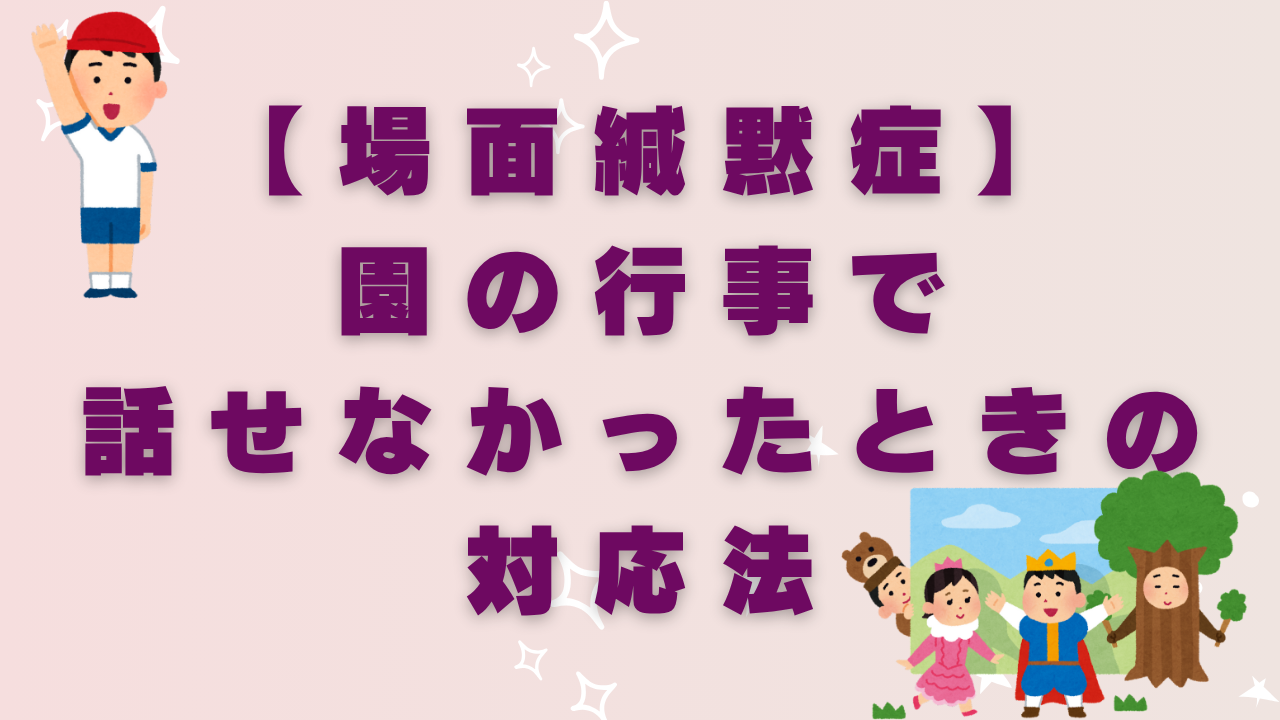
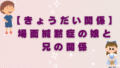
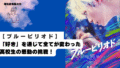
コメント