![]()
私の大好きな小説が坂木司さん著書の『和菓子のアン』シリーズなのですが、1章ごとにテーマになる和菓子が美味しそうで美味しそうで、、、
和菓子の大半は生ものなので実際に店舗に出向いて購入することが一番なのは重々承知の上で都合の良いときにネットで購入して食べたい!!と思い自分のための健忘録の意味も込めてまとめてみました。『和菓子のアン』好きな方や和菓子好きの方の参考になれば幸いです。
ちなみに和菓子のアンとは↓
デパ地下の和菓子屋で働き始めた梅本杏子(通称アンちゃん)。 プロフェッショナルだけど個性的な同僚と、歴史と遊び心に満ちた和菓子に囲まれた、忙しい日々が始まります。 謎めいたお客さんたちの行動の真相をさぐるミステリー的面白さと、青春小説の瑞々しさ満点のストーリー。
和菓子のアン
主人公の杏子が高校卒業後やりたいことを見つけられず、ニート寸前のところでデパ地下にある和菓子屋”みつ屋”でアルバイトを始め、そこで出会った男勝りな椿店長と少し乙女な職人気質の立花さんと連日急いで上生菓子を買っていたOLの”おとし文”の意味を推理するお話。
おとし文
若葉の時期は昆虫にとっても新しい産卵の時期。 オトシブミという昆虫は柔らかい若葉に卵を産み付け葉っぱをまるでゆりかごのようにくるっと巻いて地面に落とすのです。 その様子はまるで密かに書き落とした恋文のよう、、そこからの「落とし文」という和菓子の銘です。(出典https://www.kiriki-k.com/blog/57041/#:~:text=%E8%8B%A5%E8%91%89%E3%81%AE%E6%99%82%E6%9C%9F%E3%81%AF%E6%98%86%E8%99%AB,%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E5%92%8C%E8%8F%93%E5%AD%90%E3%81%AE%E9%8A%98%E3%81%A7%E3%81%99%25E3%2580%2582)
一年に一度のデート
みつ屋で働き始めて初めての夏。お中元にお盆のお土産と慣れない繁忙期に杏子は大忙し。そんな中訪れたのは毎週季節の上生菓子と松風を一つ買う穏やかなおばあさん。そのお婆さんの服装は白と黄色もしくは白と緑という少し変わった組み合わせで、、、8月13日だけいつも買う松風ではなく旧暦の七夕のお菓子に変更した理由は?椿店長から聞いた松風の意味に胸が切なくなる。
松風
萩と牡丹
秋のある日店番をしている杏子の元に訪れたのは、龍や鯉の描かれた派手なセーターを着た三分刈りのサングラスのおじさん。そのお客さんは、試食を食べれば”菓子が泣くぞ”と言い他のお菓子にも”腹切りだ、売り物にならない”と言ったりなんとも物騒。しかも毎日来店されて、おはぎを買った日に言った”ちゃんと半殺しになっているんだろうな”という言葉に杏子は意味がわからなく震え上がります。そのことを椿店長、立花さんに話すとなんと全て和菓子用語と判明。源氏物語も交えながらおはぎの名前の七変化についても描かれています。
おはぎ
おはぎは、もち米(またはもち米とうるち米の混合)を炊き、軽くついて丸め、小豆餡、きな粉、すりごまなどをまぶした和菓子です。 彼岸の時期に作られることが多い、伝統的な日本の餅菓子の一種で、萩餅の女房詞(女性が使う言葉)でもあります。
↑プレゼントにも最適な綺麗なおはぎや
↓定番のおはぎもネットで購入できます。
甘露家
みつ屋でアルバイトを始めてから半年の杏子は初めて遅番に入ることに、時間帯が変わることで客層もデパートの雰囲気も変わっており、そこでお酒売り場の生き字引こと楠田さんや、みつ屋の近くの洋菓子店の桂沢さんとと出会う。慣れない遅番で徐々に見えてくるロス問題や他店の賞味期限改ざん疑惑、突如勃発した火災など様々なトラブルに見舞われながらも美味しいお菓子の知識と駄洒落混じりの推理で乗り越えていきます。今回はあまりテーマのお菓子といったものがなかったのでこのタイトルの元となった田舎家をご紹介いたします。
田舎家
かやぶき屋根の家を模した形状で、窓や垣根が焼印で描かれているものが一般的です。季節の花や葉などを添えて表現されることもあります。

練り切りや求肥を使うことが多いからかネットでの販売を見つけることができず、店舗での購入となりました、、、
辻占の行方
辻占
辻占とは、お祭りや市の日に辻(交差点)に立つおみくじのことで、江戸時代に流行しました。
辻占いせんべいは、そのおみくじを小さな紙片にして、せんべいの中に入れたもの。

今回は『和菓子のアン』1作目に登場したお菓子についてまとめてみました。まだまだ和菓子のアンシリーズがあるので後日まとめてみます。
優しい雰囲気に美味しそうな和菓子。どちらも最高です。
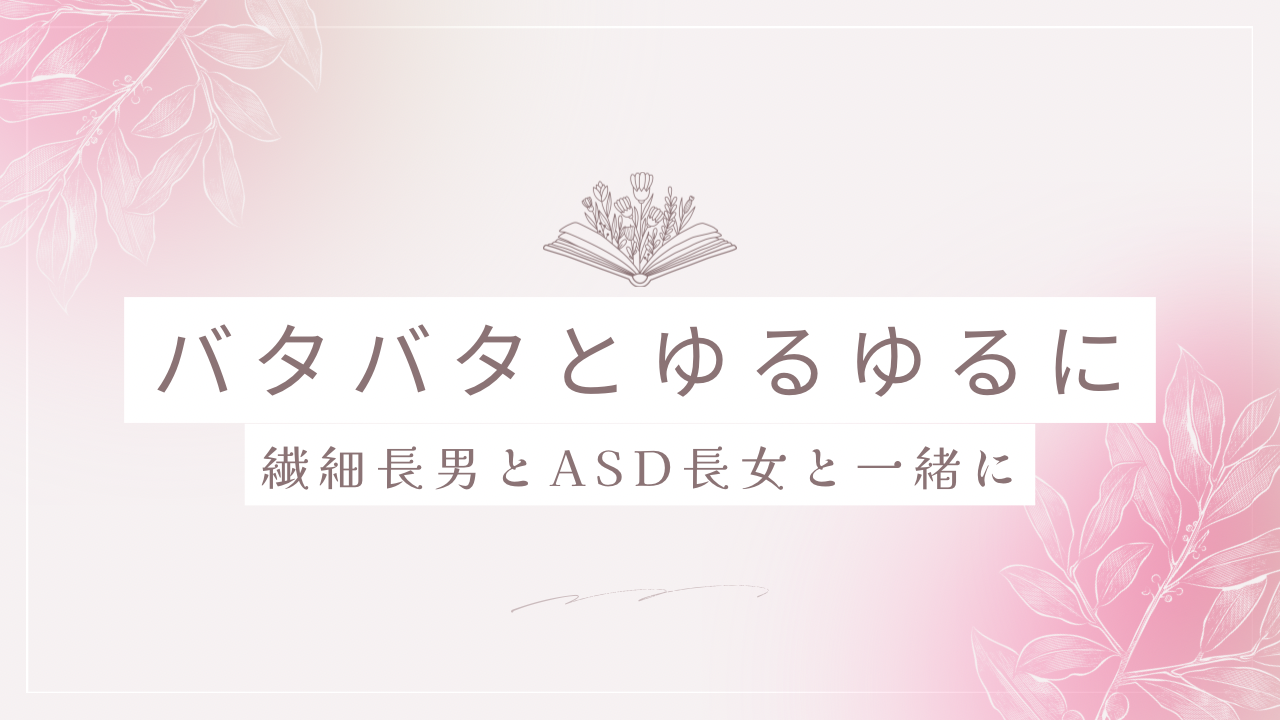








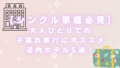
コメント